「ほんだし®」といえば茶色の顆粒です。ところでこの顆粒、何からできているかご存知でしょうか?
これ、あまり知られていないそうなんですが、「ほんだし®」のおもな原料は「かつお節」です。
しかも、厳選された「カツオ」を、「ほんだし®」専用に丁寧に燻(いぶ)し分けた本物の「かつお節」。
「ほんだし®」は味の素社の川崎工場(神奈川県川崎市)と東海工場(三重県四日市市)で製造されていますが、その原料となる「かつお節」は、「ほんだし®」誕生時から55年間、おもに静岡県焼津市にある「株式会社柳屋本店」でつくられています。
今回は、その柳屋本店を取材し、味の素社の「ほんだし®」ブランド担当者である三科光彦さんと柳屋本店の職人の皆さんとの座談会を行いました。
取材を通じて感じたのは、おいしい「かつお節」をつくるために、職人の方の経験・技術・感性が活かされていること、そして、自然の恵みを存分に活かす工夫を凝らしているということ。そりゃあ「ほんだし®」がおいしいはずですよ。
いったいどういうことでしょうか。記事をお楽しみください。
静岡県焼津市にある「柳屋本店」をたずねてみた
静岡県焼津市にやってまいりました。

JR東海道線「焼津駅」南口前のカジキマグロの銅像の近くに足湯がありました。加水・加温していない「焼津温泉」の源泉をダイレクトに楽しむことができます
静岡県焼津市は、東京から西へ約200キロメートル、名古屋から東へ約170キロメートル、まさに東京と名古屋の中間に位置する日本有数の港町です。
焼津市には「焼津港」「小川港」「大井川港」の3つの港がありますが、そのなかでも「焼津港」は、全国屈指のカツオの水揚げ量を誇っていることで有名です。
柳屋本店は、明治初年(1868年)創業。焼津港に水揚げされる「カツオ」からこだわりの「かつお節」をつくり続けて150年以上。
昭和40年代(1960年代後半)に味の素社が柳屋本店に協力を仰いだことが「ほんだし®」の誕生につながります。

工場には古くから使われている看板。富士山と丸に「八」の赤いマークは柳屋本店の屋号である「ふじまる八」を表現しています
かつて、その製造方法は機密情報だった!かつお節とは?
日本人にとって「かつお節」はとてもなじみのある食品です。かつお節は、カツオを煮た後に、燻(いぶ)して乾燥させたものです。
日本では、弥生時代あたりから「堅魚」というかつお節の原型のようなものがつくられており、日本最古の歴史書「古事記」(712年)にもその名前が登場しています。
現代のかつお節は、江戸時代に紀州出身の漁師が、土佐で確立した「土佐節」にルーツがあるといわれています。かつお節は由緒ある高級品として扱われ、その製造方法は藩の機密事項とされていたそうです。
明治に入り、その製造方法が公開され、焼津にも伝わり、独自の進化を遂げ、焼津のかつお節は鹿児島県と並ぶ産地となりました。
かつお節には、うま味成分である「イノシン酸」が多く含まれています。また、9種類の必須アミノ酸がすべて含まれているため、日々の食事に取り入れることで栄養補給にも役立ちます。
こだわりの「かつお節」ができるまで<柳屋本店の場合>
では、柳屋本店の工場でかつお節をつくる工程を簡単にご紹介しましょう。
結論からいうと、時間と手間をかけてかつお節をつくっていきます。一部機械化されているとはいえ、基本的には150年以上前から続けられている工程によって、うま味と風味が凝縮された良質なかつお節ができあがります。
買い付け
焼津港で水揚げされたカツオを買い付けます。この買い付けが非常に重要なんだそうです。
柳屋本店のグループ会社で買い付け担当である「株式会社富士冷」のスペシャリストたちが長年培った経験に裏打ちされた技術と感性で、「ほんだし®」に適したカツオを選んでいるそうです。
解凍
冷凍されたカツオを工場に運び、ひと晩かけて水で解凍します。解凍する際は定められた温度の下で行われます。
このとき、独自の「高イノシン酸製法」という解凍手法を用いています。これは味の素社と柳屋本店で特許を取っている技術です。この解凍手法もおいしさの秘密のひとつだそうです。

解凍前のカツオの様子。解凍作業も厳しいルールをもうけ、うま味成分の保持とヒスタミン生成防止のため一定の温度管理で行われます。また近年は海洋プラスティック汚染の影響もあり、異物混入には細心の注意を払っています
生切り(なまきり)と篭立て(かごたて)
次は生切りと篭立てです。
解凍されたカツオの頭部と内臓を、一匹ずつ機械にかけてすばやく除去していきます。だいたい1日で2万匹のカツオをさばいていくそうです。

ヘッドカッターで頭を切り落とした後に、ドレスマシンを使い、腹膜内臓を一気に除去します。
頭部と内臓を取り除いたカツオを「煮かご」に入れます。「篭立て」という作業です。このときカツオの腹を上にして並べるのがポイントです。

カツオを煮るときに水気が下から上に沸き上がるので、お腹を下に置くと肉がこぼれ落ちてしまうため、必ずお腹を上にして並べていきます
ひとつの煮かごに500~600kgのカツオが詰め込まれると、パレットハンガーで吊り上げられ、次の「煮熟」という工程に移ります。
煮熟(しゃじゅく)
煮かごに詰めたカツオを、釜に沈めて煮ます。これを「煮熟」といいます。
柳屋本店には16個の釜があります。98℃の温度でたんぱく変性するまでじっくりと煮込みます。煮熟は、カツオを燻(いぶ)す前の大事な工程です。

煮熟が終わり、ちょうど煮あがった煮かごが出現!湯気がぶわっとひろがり、カツオのいい香りが昼食前の私たちの胃袋にしみわたります
この煮熟のときに出る煮汁もカツオエキスとして「ほんだし®」の原料などに使用されています。
煮熟が終わると、放冷場という場所で冷やします。その後、手作業で一匹ずつ煮あがったカツオを2つに割って(大きいものは4つに割ります)中骨などを取り除いていきます。


一匹ずつ手作業で、中骨などを取り除いていたカツオをせいろに並べていきます。また取り除いた中骨は「毎日カルシウム・ほんだし®」の原料に使用されます
焙乾(ばいかん)
さて、かつお節づくりのクライマックスといえば、焙乾(ばいかん)です。薪を焚いてカツオを燻す(いぶす)工程です。

焙乾前に並べられたカツオ。1週間から10日ほどじっくり燻されます
焙乾の目的は「乾燥」と「燻し香(いぶしこう)の付与」です。柳屋本店では、厳選されたナラとクヌギの薪を焚いて、燻しながら乾燥させています。
柳屋本店では、工場の建屋の最下層である地下の火床から上に向かって、直火の自然対流でカツオに熱や煙を送り込んでいます。

これは足元を照らす照明ではなく、地下から轟々と燃え上がる炎!熱気と煙と音に圧倒されます
地下の火床は8か所。直火で加熱と燻付け(くんづけ)をします。仕上がりまで数週間かけて燻しつづけます。

火床に潜入!とにかく熱気と煙がすごいです。でも薪のせいなのか、せき込むような煙ではなく、心地よい香ばしさを感じる煙でした。毎日お昼ごろから火入れをして、一日に数回薪をくべています
柳屋本店の焙乾は、通常のかつお節工場では行わない手間をかけ、特殊な作業を行っています。その理由は、味の素社の規定した温度で燻すこと、そして厳密な微生物検査をクリアするためだといいます。
「1日に2万匹を購入して、4つに分けたら8万本のかつお節ができるんですが、もし8万本のうちの1本だけでも微生物が検出されるとなると、その8万本は納品できません。それくらい味の素社の衛生・品質管理の基準は厳しいんです」(柳屋本店 加工用事業部・研究開発部部長 鈴木基裕さん)
そのため、柳屋本店では、通常の工場の3~4倍の作業者を配置しています。さらに作業する日の天候、温度、湿度などによっても管理の方法は変わってきます。薪の数や風の送り方などを調整し、熟練した職人の感性と手間をかけた管理によって、おいしさはもちろん、安全・安心なかつお節をつくることを徹底しています。


焙乾が終わって、出来上がったかつお節。水分が抜けてサイズも元のカツオから1/5くらいに縮んでおり、カットするとまるで宝石のようにキラキラした断面が現れます
柳屋本店では「ほんだし®」専用として「極深燻し」「深燻し」「浅燻し」の3種類のかつお節を味の素社に納品しています。
薪組み
焙乾で使う薪についても紹介しましょう。柳屋本店では、薪の選び方も徹底しています。

薪を焚くときに崩れてしまうと火事になる危険性もあるため、形状を選別して、崩れないように組み合わせます
薪は、ナラとクヌギを使っています。「ほんだし®」向けのかつお節は香りを強くしてほしいという味の素社の要望を受け、厳選された木材を使用しています。
さらに、「ほんだし®」に豊かな香りを与えるため、柳屋本店では、他社の数倍の量の薪を燃やしており、そのかつお節はまさに究極の香りを実現しているといいます。
「これ以上燃やすと工場が燃えてしまいます(笑)。最大限に燃やすので、非常にかつお節の香りが強いです。これはどんな会社にも負けません」(鈴木さん)
スペシャル座談会〜究極の「かつお節」への飽くなき追求
味の素社の「ほんだし®」担当者の三科光彦さんと柳屋本店の「かつお節マイスター」3名とで座談会を行いました。そこには、メーカーとサプライヤーの立場を超え、お互いに切磋琢磨していく姿と、お客様に「おいしさ」を提供するために努力を重ねていく思いがありました。
「ほんだし®」ブランドマネージャー

味の素株式会社
食品事業本部 コンシューマーフーズ事業部 シーズニンググループ
三科 光彦
いぶし銀の工場長
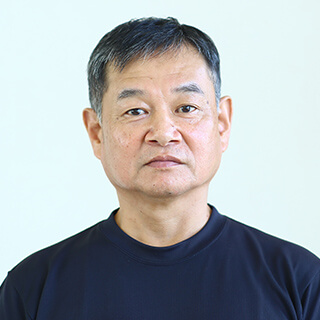
株式会社柳屋本店
加工品事業部 工場長
小川 幸広氏
焙乾と品質管理の専門家

株式会社柳屋本店
研究開発部 次長
日吉 渉氏
カツオの目利き

株式会社富士冷
原料部原料課 係長
大塚 陽太氏
 三科さん
三科さん
大塚さんは買い付け担当ですね。どういうことを意識して、カツオの買い付けをされていますか?
 大塚さん
大塚さん
まず「鮮度がいいカツオ」かどうか。その次に、かつお節に最適な「脂が少ないもの」を選びます。
 三科さん
三科さん
冷凍で水揚げされたカツオの鮮度って、どうやって見分けるんですか?見た目で?
 大塚さん
大塚さん
お腹ですね。魚のハラモ(お腹の部分)を見て、出刃包丁を使ってハラモを削って色目を見ます。ピンク色をしていると鮮度がいい。鮮度が悪くなると灰色っぽくなっています。

 三科さん
三科さん
買い付けされたカツオは工場に運ばれてくるわけですが、工場長である小川さんが作業するうえでこだわっているポイントを教えてください。
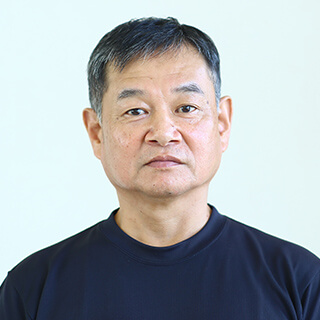 小川さん
小川さん
まず、買い付けしてもらったカツオの鮮度を失わない解凍。解凍水の温度であったり、カツオが傷まないような方法で細心の注意を払って解凍します。この工程はとても重要です。
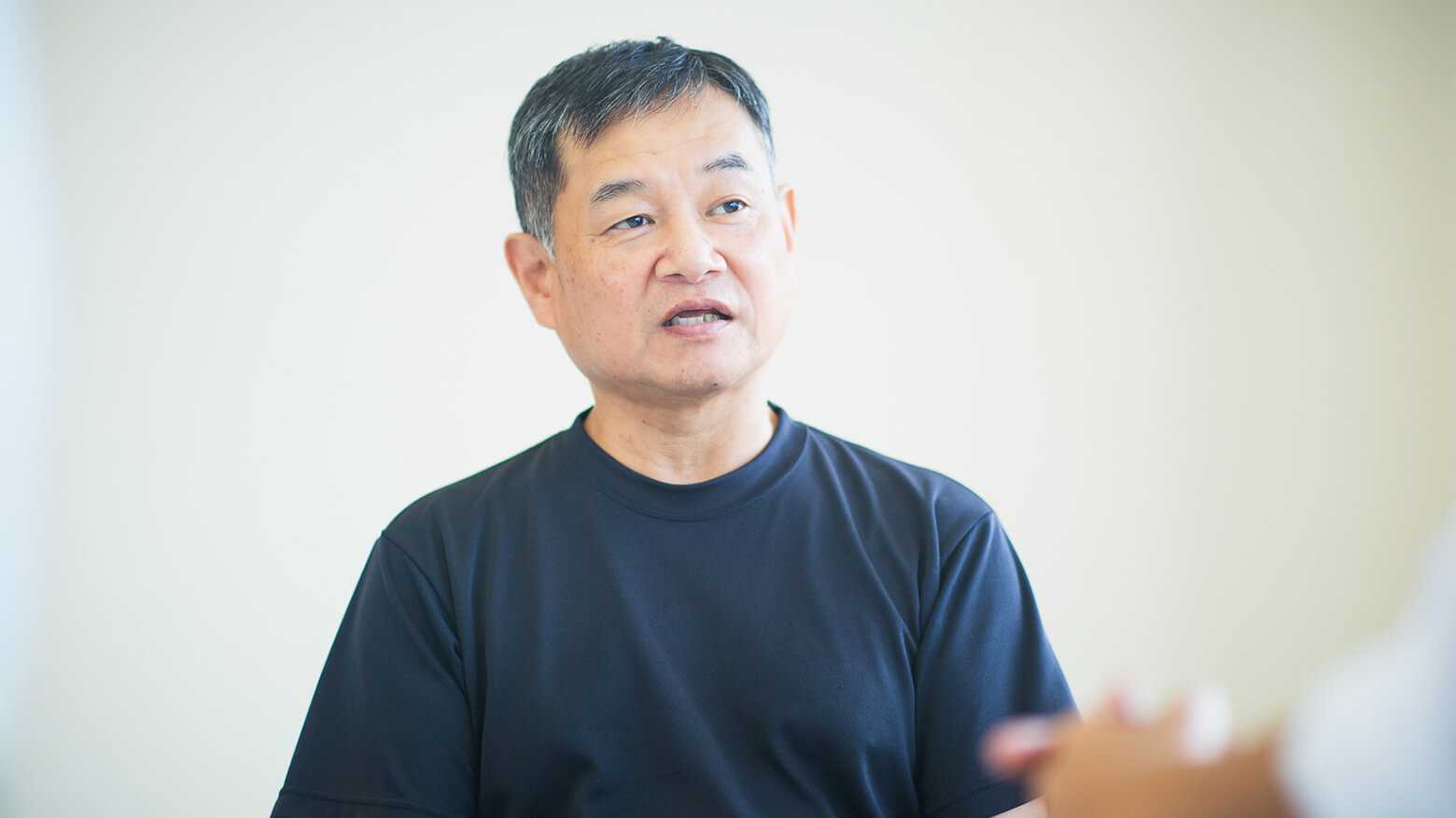
その辺に生えている木の薪を使っても「ほんだし®」にならない
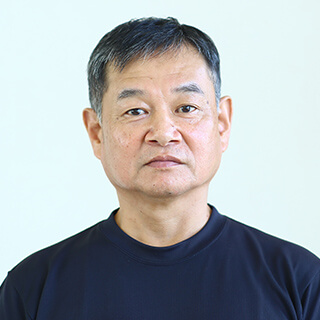 小川さん
小川さん
そして、焙乾。燻す作業ですね。味の素社の厳しい基準にあわせた水分、決められた燻臭成分をつけるという工程です。薪も大事です。その辺に生えている木の薪を使っても「ほんだし®」にならないんです。
 三科さん
三科さん
それはなぜでしょうか?
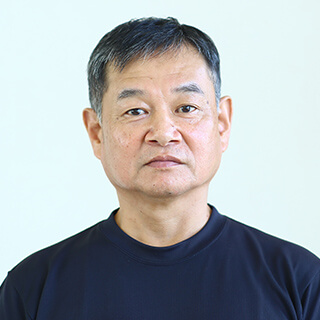 小川さん
小川さん
味の素社の検査をクリアするためには、しっかり選別した薪を使わないとダメ。高い香りがつきません。

小川工場長自ら薪をくべています。燃えさかる炎に立ち向かうその姿はヒーローのようにみえました
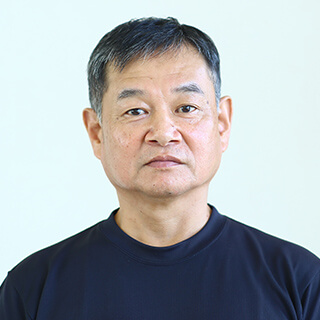 小川さん
小川さん
薪は決まった場所で、決められた種類のものを使います。伐採したら必ず乾燥させて決められた水分量まで下げます。そうすると、目に染みない煙になる。煙が目に染みるような薪を焚くと、かつお節に苦味が出たり、風味が曖昧になったりします。薪の管理の徹底が、おいしい「ほんだし®」につながっていくんです。
3種のかつお節をブレンドした「ほんだし®」の強みとは?
 三科さん
三科さん
「ほんだし®」の特徴といえば、3種のかつお節をブレンドしていることですが、日吉さん、この3種について教えていただけますか?
 日吉さん
日吉さん
「ほんだし®」の3種のかつお節、これは品質的に大きな特徴ですし、商品の強みであると思います。私たちは「極深燻し」「深燻し」「浅燻し」の3種類のかつお節をつくって味の素社に納品しています。

 日吉さん
日吉さん
「深燻し」はいわゆる通常のかつお節、「極深燻し」は薫香(くんこう)が非常に強いかつお節、「浅燻し」は少し甘いような香りが出るかつお節ですね。その3種類をそれぞれの品質基準にあわせ、味の素社に提供できるように努力しています。毎日出来上がるものを評価基準に照らし合わせて問題がないということをチェックし、合格となったものを納品しています。
 三科さん
三科さん
どのような点が難しいと思いますか?
 日吉さん
日吉さん
薫香の強さにもいろいろあって、こう、味噌汁を味わうとき、初めにシュッて入ってくるかつお節の香り。「ほんだし®」では、この成分をとても重視していると思います。

 日吉さん
日吉さん
また、少し飲んだ時にちょっと甘く広がるような香りですね。私たちはそれぞれの特徴を生かした香りを意識して、かつお節の燻し方を調整しています。
―――そもそも、この3種のかつお節をブレンドすることになった背景は?お話をうかがうと工程も手間がかかるし、かなり贅沢な仕様だといえますよね。
 三科さん
三科さん
生活者のライフスタイルも変化しています。近年では家族で食事をする時間が違うというご家庭も多いと聞いています。調理して時間が経った味噌汁を温めなおしても、かつお節の燻しの香りが飛ばないようにするため、「ほんだし®」はそれまで2種だったかつお節を、2007年(平成19年)から3種のブレンドという形で展開しています。それ以来、柳屋本店に3種の燻し分けをつくってほしいとお願いしてきました。

 三科さん
三科さん
さらに味噌汁だけでなく、いろいろなメニューを楽しんでいただきたい。たとえば、「ほんだし®」でつくる和風パスタ、トースト、親子丼など。和の食卓が広がっていく状態を、柳屋本店の皆さんとともにつくりだしたいと思っています。
―――「ほんだし®」が定番であり続けているということは、「変わらないから」でなく、社会のライフスタイルの変化にあわせて「どんどん進化してきた」から、ということなんですね。
 三科さん
三科さん
はい、生活者をきちんと観察していくことでさらに進化していくでしょう。そのときは、柳屋本店の皆さんとともに新しいものをつくっていく。皆さんにはさらに新しいご要望を......それはもしかしたら厳しいものになるかもしれませんが、ご協力いただきたいと思っています。
―――小川さん、これまでも多くの味の素社のリクエストに応えてきたと思いますが、三科さんの意見を聞いて「勘弁してくれ」となりますか?
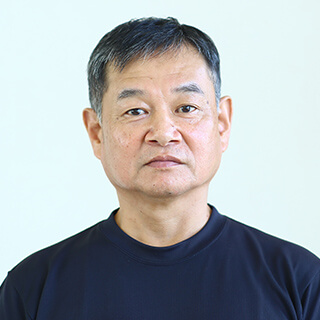 小川さん
小川さん
いいえ!それは私が働いていることの励みのひとつですから。

かつお節づくりはサステナブルな循環型のエコシステム?
―――先ほど工場で小耳にはさんだのですが、「かつお節は捨てるところがない」というのは本当ですか?
 日吉さん
日吉さん
工場で切り落としたカツオの頭部と内臓はミンチ状にします。その後、発酵と加工をして、魚醤(ぎょしょう)という液体調味料として使っています。また、煮熟したときに出る煮汁についてはカツオエキスとして「ほんだし®」に利用したり、魚醤と一緒にしてオイスターソースのエキスとしても活用しています。
―――取り除いた中骨なども活用されているとか?
 日吉さん
日吉さん
そうです。ちょっと加工は必要になりますが「毎日カルシウム・ほんだし®」の原料に使用されています。

 日吉さん
日吉さん
さらにどうしても活用できない部分は飼料や肥料として活用します。
 三科さん
三科さん
肥料として茶畑で使用されているというのも聞いています。ですので、廃棄するものはありませんね。
―――すごい!圧倒的ですね。また焙乾で使用する薪についてもサステナブルに取り組んでいるそうですね。

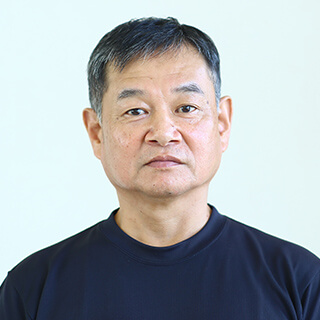 小川さん
小川さん
薪につかうナラの木は、樹齢が30年から40年のものだけを伐採してます。 伐採した切り株からまた新しい芽が再生してきます。 そのスピードがとても早いんです。私たちは自然のものを使っていくので、山を守り、資源を大事にしなきゃならない。

 三科さん
三科さん
森がちゃんと循環するように。
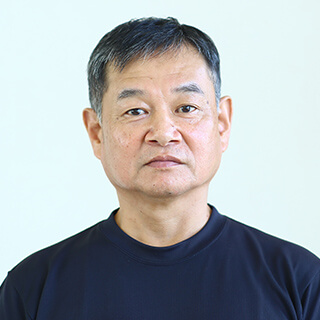 小川さん
小川さん
薪に使う木はローテーションを組んでしっかり育てれば再生して回ります。私たちもたくさんの薪を使いますから、同時に森をしっかり育てるということは大切な使命です。
 三科さん
三科さん
伐採して育てて、木や山を元気にさせるという観点でいうと、山の栄養が海に流れていくことになり、魚にとってもいい状態になります。ひとつのブランドが、資源を大切に使い、循環していく。大げさかもしれませんが、こうした取り組みを通じて社会課題の解決にも貢献できたらうれしいですね。
「ほんだし®」とかつお節が共創する未来
―――「ほんだし®」55周年を迎え、これからの展望をお聞かせください。
 三科さん
三科さん
製品とコミュニケーションの話があります。製品については2025年(令和7年)の8月に品質と味覚の改定を行いました。最近、みそ汁に麹歩合(大豆の使用量に対する麹の割合)の高い味噌を使う方が増えています。麹が多いと甘みが強くなり、相対的に「ほんだし®」の魅力である燻しの香りが弱まってしまう可能性があります。
そこで今回の改定では、最初に感じるかつお節の香りを強くして、麹の甘さに負けないようにしました。今後もどんどん生活者の実態に合わせた改訂をしていきます。

―――コミュニケーションについてはいかがですか?
 三科さん
三科さん
「ほんだし®」が本物のかつお節からできていることを知らない人が多いということと、「ほんだし®」を味噌汁にしか使わないということ。この2つがすごく大きな課題です。こうしたイメージを払しょくするための活動はどんどん発信し続けていきます。2023年~2024年(令和5~6年)に制作したTVCMでもこの2つのテーマを訴求した内容を発信しています。
「ほんだし®」 店主篇 30秒 CM 賀来賢人 出口夏希
店主に扮した賀来賢人さんが本物のかつお節からできている「ほんだし®」を使った店自慢の味噌汁をお客さんである出口夏来さんにふるまいます
「ほんだし®」 釜玉パスタ篇 TVCM 30秒
賀来賢人さんが「ほんだし®」を使ったアレンジレシピを紹介しています。この映像に流れるかつお節工場はもちろん柳屋本店のかつお節工場です
 大塚さん
大塚さん
原料の調達部門としては、安定して品質の良い魚を工場に供給することが一番大事なポイントだと思います。 自然が相手ですから、年によって魚が穫れたり穫れなかったりしますが、原料を安定して保有し、状況を鑑みながら計画的に買い付けをしていきたいと思っています。

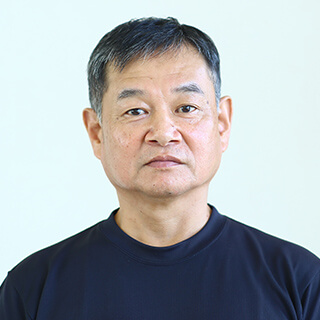 小川さん
小川さん
工場としては、決められたことを確実に行うこと。そしてそれを持続していくことです。あと大切なことは、私の知識をしっかりと後輩たちに伝えていくことが大きな課題です。100年、200年、この文化が続いていくことを目指していきたいです。
 日吉さん
日吉さん
製造する環境や、魚の環境(カツオが育つ環境や漁獲量)なども変わっていくなかで、継続的に安定してかつお節を提供し続けることの難易度が年々上がっていると感じています。日々の管理はもちろんですが長期的に安定して高品質のかつお節をつくっていけるような工場づくりを目指していきたいです。
―――3種のかつお節が4種になる未来があるかもしれませんよね?
 日吉さん
日吉さん
そうですね、はい、お話しをいただければ、ぜひやりたいと考えております。
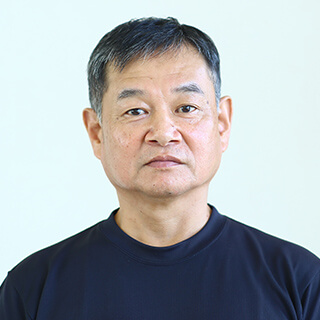 小川さん
小川さん
常に探求心を持って。柔軟にね。

今回の取材は、当社の公式ファンコミュニティ「味のもト~ク」・AJINOMOTO PARKとのコラボ企画として共同取材を行いました。
そちらでは柳屋本店の臨場感あふれる工場見学や従業員の皆さんと楽しいトークなどを動画を含めてお楽しみいただけます。※随時更新予定です。
さて、取材終了後、柳屋本店の経営する食堂「やなぎやカフェ」にお邪魔しました。
ランチは3種類あって、トッピングやカスタマイズが楽しめます。(写真は「選べるだし茶漬けセット」2025年8月現在)

さらに、カウンターに設置された削り節マシンで削りたてのかつお節が食べ放題。隣接する柳屋本店直売所では柳屋本店のかつお節をはじめたくさんの商品を販売しています。
ぜひ、焼津にお越しの際にはお立ち寄りください。おすすめです。
やなぎやカフェ
〒425-0035 静岡県焼津市東小川2丁目1番10号
https://yanagiyacafe.com/

三科 光彦
味の素株式会社 食品事業本部 コンシューマーフーズ事業部 シーズニンググループ
2012年入社。営業を経て、2021年よりマーケティング部門で「味の素®」「アジシオ®」などを担当。現在は「ほんだし®」のプロダクトマネージャーとして、皆さまの日々の食卓にワクワクや発見を届けることを目指しています。常に「My ほんだし」を持ち歩き、和の新しい可能性を探求中です。
2025年11月の情報をもとに掲載しています。

関連リンク